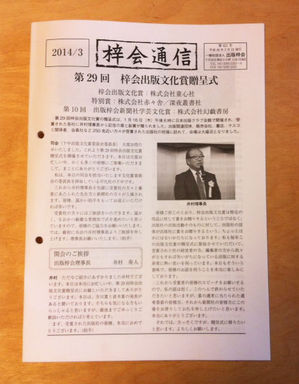今年の1月に弊社が梓会出版文化賞特別賞を受賞させて頂いた際、贈呈式会場にて代表 姫野希美が行った受賞スピーチが3月の梓会通信に掲載されました。
下記に全文を紹介させて頂きますので、普段より赤々舎の本をご愛読頂いている皆様(たいへん感謝致します)、そして弊社の本と出会いあらたにページを開いてくださるかもしれないまだこれから先の多くの皆様に、生きている場所に息づく本をお届けしたいという所志を、是非ご一読頂ければと思います。
============================================================================
第29回梓会出版文化賞特別賞を受賞して
ーー写真という大きな問いの器ーー
文・姫野希美
●衝動的な出発
この度は梓会出版文化賞特別賞をいただくことができ、光栄に存じます。赤々舎は2006年の春に設立し、もうすぐ8年が経とうとしております。スタッフは当初は私ともう1名、そして今は私も含めて3名という小さな出版社です。これまでに約110冊の本を刊行し、その9割以上が写真と現代アートの企画出版です。
私は10年ほど、京都の版元青幻舎にお世話になり、そこではデザインや建築も含めて美術の幅広いジャンルの本を制作していました。そんななかで、当時20歳代だった写真家たちとの出会いが鮮烈で、巻き込まれながら、覆されながら、写真集をつくることに大きな刺激を受けました。写真集やアートの本を集中してつくりたい、いま生きている作家とやりとりをしながら一冊ずつを生み出したいという気持ちから、勝手を言って独立させていただきました。もうひとつ、当時から写真集は採算がとりにくいものでしたが、それでもその売りにくいものこそ売っていきたいという青臭い気持ちがありました。とは言え、なにか具体的な目処や計画があったわけではなく、自分が40歳となるのを目前にして、残された時間で何冊、納得のいく本がつくれるだろうという衝動にも似た行動でした。
こうして振り返りますと、いまだ端緒に過ぎないという思いでいっぱいです。幸い、この8年は、素晴らしい作家との出会いに恵まれ、彼らに導かれるようにして本をつくることができました。ほとんど業界や潮流を意識せず、少なくとも私ひとりはこんなに心動かされたということを出版の糸口にしてきたように思います。
●大きな問いの器
心動くということは、その作品はわけがわからないものであるということです。わけがわからない、混沌としたエネルギーを、私はとりわけ写真の力だと考えています。イメージの生命体としての在り方が、いちばん写真にはあるような気がしています。だからこそ、社会のなかに、「大きな問いの器」として写真を差し出すことができればと願っています。
昨年末の大きな喜びとして、先ほど五十嵐太郎さんのお話にも出ました志賀理江子さんの『螺旋海岸』が、世界の「Photo Book of the Year」で幾つもベスト1に推され、大橋仁さんの『そこにすわろうとおもう』など他の写真集も、多くの賞でノミネートされました。志賀さんは宮城県の北釜という村落に数年間を暮らし、地域のカメラマンとして祭などの行事を記録しながら、作品を制作し続けてきました。それは北釜という土地の固有性を物語るものではなく、写真というメディアとは何か、土地とともにある暮らしと表現とは何かについて、志賀さんが自問し追求してきた問いそのものの現れでした。また大橋さんの写真集は、繰り広げられる性の現場が大きな話題を呼びましたが、その肉の姿を通して、写真による人類史を独自に描き出そうとした大作でした。
これらの写真集は説明もなく、存在としては忽然と世界の読者の前に出現します。見る人を大きな渦に巻き込むようなエネルギーは、もちろん作品の力であるとともに、写真集そのものが放つ強度も深く関わっていると思われます。日本において写真集はカタログではなく、作品を体現するものとして、デザイン・印刷・製本まで一体になりながら創意を
尽くして発展してきたものだからです。
赤々舎は世界に出ていこうというような意気込みからはむしろ遠いのですが、ただ当たり前のこととして、世界の何処ともここは地続きであると思い、一冊一冊を送り出していきたいと思います。
●生きている場所に息づく本を
写真、写真と申し上げておりますが、本当に気がつけばそうなっていたという具合です。私はカメラを持っておらず、写真の教育を受けたこともありませんが、写真によって思いがけない処に出てしまい、その都度わけもわからず身を投じているような感覚があります。編集者やディレクターと呼ばれるような役割でもありますが、その呼び方を自分に関して避けてきたのは、私はあくまで媒体に過ぎないという思いからでした。ある写真が孕んでいる可能性が本という姿になるときの、透明な媒体として居合わせている、その位置は変わらないような気がします。
これからは写真やアートを核にしつつも、自分がもともと魅了されていた詩歌やダンスなどと出会い直していけることも夢見ています。どれも書籍としては現実的な困難を伴う分野ですが、だからこそ冒険もあると信じたいのです。つい先頃、写真集や絵本の販売について、思いみることもなかったような提案を受ける機会がありました。それがどのように結実するかはまるでわからない段階ですが、そうした兆しを心から喜びたい気持ちです。世界との関わりの痕跡としてある写真、生と死の間に存在する写真であればこそ、いかなる枠や敷居も有することなく、私たちが生きている場所に本を息づかせたいと願っています。
最後になりましたが、日頃よりお力をお貸しくださり指導してくださる皆様に心より御礼申し上げます。本日は、このような挨拶の場をお与えいただき、ありがとうございました。
(1月16 日、梓会出版文化賞贈呈式会場で受賞のスピーチから、ひめのきみ/株式会社赤々舎代表取締役
============================================================================