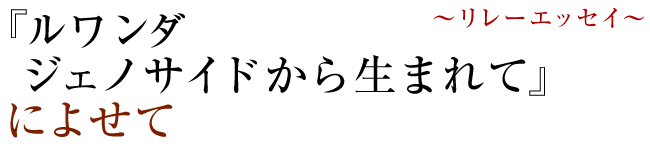
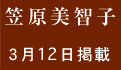

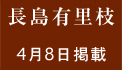
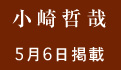
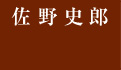
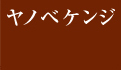
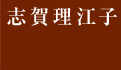

この本へのコメントを半分ぐらい書き終わったところで東北関東大震災が起き、それに起因して福島原発の事故が起きた。しばらく仕事は手につかなかったが、やることは山ほどあった。膨大な量の情報を収集し、直感を研ぎ澄まし、脳をフル回転させながらそれらを選り分け、必要なものをリストアップし、淡々とスーツケースに詰め込む。最初の数日は交通機関が止まり、仕事をしない言い訳もできたが、すぐに東京は放射能の危険に怯えながらも通常の生活を送ることに決めた。わたしなんて、通常の生活に戻ろうと腹を決めたのはつい四、五日前のことなのに。そして再びコメントに取りかかったが、まるで別の人が書いたもののように思えるし、続く言葉が出てこない。そこで思い切って古いものはゴミ箱にドラッグし、新しい原稿を書くことにした。
わたしはわたしの正しいと信じることに従って生きたい。現代社会において、他人に重大な危害を与える原因にならない限り、この自由は守られている。今回の原発事故に関しては、メディア、電力会社、学者、そして政府が正しいと思うことと自分のそれは、初めから違っていたが、わたしは自分の判断が間違えているとは思わなかった。他者と考え方の相違がある場合、両者がお互いの意見を尊重し、認め合うのが社会の流儀だと思っていた。けれども実際は違っている。世の中の主流あるいは権力を司る集団と対立した考えを持つ自分を信じることには、思った以上の困難が伴い、わたしは自分の考えを様々な形で否定された気がしたし、自己嫌悪や不安に陥らざるを得なかった。
一夜にして、世界がすっかり変わってしまうなんていうことはないと思っていた。地震の前、わたしはルワンダの女性たちと自分の共通点を、女性であることに集約して文章を書いていた。たとえ彼女たちの壮絶な経験を理解することができなくても、同じ女性という立場から共感することは可能だと考えたのだ。例えば、彼女たちの何人かが語っていたように「もし子供が父親の性質を受け継いでしまったら」という不安は、離婚したわたしのものでもある、なんていうことを書いていた。そうしながら心のどこかでは、彼女たちに起きたようなことは自分の身に起きなかったし、これからも決して起きないと「知っていた」。死や、決定的な傷を負うような経験を、先進国の日本に生まれ育ったわたしがする日は決してこないだろうと、何の根拠もなく、漠然と思っていた。彼女たちに対し、自分は強者であり彼女たちは弱者であるというような、何か非常に気まずい優劣関係を少なからず意識していた。
この三週間で、その気持ちはゆっくりだが完璧に打ち壊された。自分の外側から暴力的な方法で命がもぎ取られる状態が、初めて具体的に想像できたのだ。なぜ社会がそのような状態に陥ってしまったのかを考える余裕はなく、ただ、どうすれば最悪の事態を避けれるのかを考える数日を過ごした。手だてを知るために、自分は何を信じるのかを一から洗い出し、大きな力にコントロールされそうな意志を立て直し、本当の考えを隠さなくてはならない圧力に耐えた。翻弄され、悩み、敵なのか見方なのかと探りながら人と話し、次の行動を瞬時かつ直感で判断しなくてはならなかった。じっくり考える時間はなかった。そして、二週間半経ってようやくひとつの指針に辿り着いた。
その指針とは、なによりも命を優先するというものだった。「命」と言うとき、わたしはまず自然と我が息子のことを思った。いままでずっと、わたしのいるところが彼の居場所になり、わたしの食べるものが彼の体をつくってきた。責任はすべて親である人間の上にある。それはときに致命的な重荷だが、同時に、常にわたしの生きるという活動を根本から支えてもきた。
不測の事態が起き、緊急の判断を要するときでも人は、その一瞬前までの生活を捨てて行動することを躊躇する。目に見えない放射能(=存在しないかもしれない悪)を怖れて、子供にマスクをさせたり、外遊びを禁止したり、雨の日に学校を休ませて自宅待機したり、ひいては遠いところへ避難したりする必要が本当にあるのだろうか。わたしの心は「ある」と言い、世間は「ない」と言う。わたしが社会を信じないとき、そこには制裁が待っている。「女はすぐに大騒ぎする」「経済を回していくことこそが重要なのに、それを放棄して逃げるのはバカだ」「早く学校に来れるといいね」「発表会の振り付けはちゃんと覚えてくださいね」。時間がなく、どうしようもなくどっぷりと渦中に飲み込まれているとき、これらの言葉がわたしを責め、自己嫌悪に陥らせる。彼らの言っていることは、「以前」の生活においては正論だからだ。さらにそこに、「女」に貼られたレッテルからくるわたし自身の思い込みや劣等感が加担する。女であるわたしは感情的なのかもしれないし、論理的でもないかもしれない。神経質さやこだわりの強さから子供をコントロールし、大切な時間を奪っているのかもしれない。あるいは自己中心的なのかもしれないし、衝動的なのかもしれない。 しかしわたしたちはいま、重大なパラダイムシフトが起きたということに気付かなくてはならない。東京在住のわたしにとっては、原発の事故こそがそれである。いままでの価値観が通用しない世界がすでに到来し、まるで手のひらを返すように、一瞬でわたしを取り巻く世界の価値観を変え、いまも持続している。
このパラダイムシフトの経験は、写真集にうつるルワンダの女性たちに、わたしをより近く引き寄せた。すでにわたしの目線は、彼女たちのそれとほぼ同じ高さに位置しているように思える。彼女たちに何をしてあげられるのかという少々傲慢な、けれども実際はそれが妥当だと思えた感情が変わり、いまは彼女たちのまなざしが何処を見つめているのか、その行方を教えて欲しいと思う。わたしのしていることが正しいのかを、彼女たちが知っているような気がしながら、もう一度ページをめくる。
なぜ、彼女たちが自分の子供を産み、育てることにしたのか。その選択のもとには強い風当たりがあり、大きな差別があるのにもかかわらず。彼女たちの多くは、生まれてきた子を愛していると言うが、少なくない幾人かは愛せないと言う。愛しても、愛さなくても、子供を引き受けているという事実に変わりはなく、わたしにはそのことがより重要に思える。なぜなら、自分の気持ちをどう語るかということはあくまで言語の問題であり、どのような表現を選んだとしても、自分の中に渦巻く大きな葛藤を完全に表現することは所詮できないからだ。自分の過酷な過去を乗り超えるために子供と暮らす、あるいは直視できないために子供と暮らせない、そのいずれであっても、新しい命を引き受けるというその決断こそ、誰かに発明された愛という言葉が意味するものを遥かに凌ぐ何かを物語ってはいないだろうか。彼女たちは、起きてしまったことの過ちを自分で引き受けながら、それを子供たちには引き継がないことを強く望んでいる。子供と暮らさないという選択肢でさえ、そこに起因した行動にみえる。彼女たち一人一人の生き方がいま、わたしの新しい問題を自分がこれからどう引き受けるのかを考えるときの支えになっていることはまぎれもない事実だ。女性、母、社会的弱者--立場に共感できさえすれば、括り方は何でもいい―こそがぶつかる困難や示せる生き方があり、それを知り、やり遂げるためにわたしは存在すると思いたい。事実、この世の中には変えなければいけないことがあり、自分のしなくてはならないことがある。


