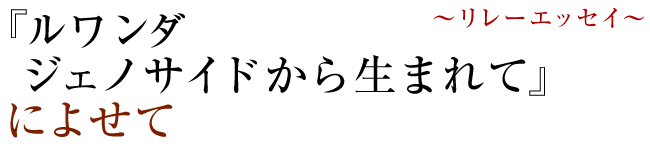
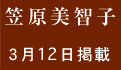

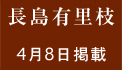
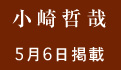
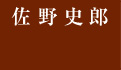
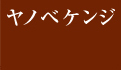
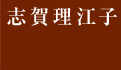

加害者に共感すること
ほとんどの母子は同じような表情を浮かべている。無表情と呼ぶほうが正確かもしれない。わずかの例外を除いて誰も笑っていない。
この目は見たことがある、と思った。思い当たったのは、パレスチナ映画『D.I』を撮ったエリア・スレイマン監督の目だ。プロモーションで来日した2003年、ティーチインの司会を務めた際に会ったのだが、イスラエル占領地区で繰り広げられる超現実主義的ナンセンスコメディとも呼ぶべき自作と同様に、四六時中ジョークを放っていた。
だが、目だけは笑っていなかった。あまりにも非日常的な日常を送っていると、ジョークが研ぎ澄まされる一方、感情は鈍化し、はては凍結されるのではないか。そんなふうに思わざるを得ないほど、外界を拒絶しているように見えた。
その目に似ている。母親たちの目も、子供たちの目も。ほぼすべてがカメラ目線で、したがってレンズを通して、我々読者を正視しているように思える。この視線にきちんと向き合うのは容易ではない。誰もが目を背けたくなるのではないだろうか。
世の中の多くの物事において、人は当事者と第三者に分かれる。それが人の手になる災厄だった場合、当事者は加害者と被害者に分けられる。つまり人災が起こった場合、人は「加害者」「被害者」「第三者」に分かたれることとなる。
『ルワンダ ジェノサイドから生まれて』の読者たる我々は、言うまでもなく第三者であるだろう。ルワンダは遠く離れている。紛争は我々が引き起こしたものではないし、関わってもいない。我々は人を襲ったことも犯したことも殺したこともなければ、襲われたことも犯されたことも殺されたこともない。だから我々は加害者でも被害者でもありえない。
同じことは同時代に自国外で起こったあらゆる人災について言えるだろう。ホロコースト、アパルトヘイト、アジア・アフリカ・東欧・中南米諸国における強権政治と虐殺、ヴェトナムやアフガニスタンや湾岸諸国への空爆、文化大革命、チェルノブイリ、天安門、9.11......。日本人にとっては、国内で起こり、被曝者がいまも苦しむ「広島・長崎」と、同じく現在進行形の「フクシマ」は事情が異なる。だが、本稿を書いている4月末時点では、被災地の方々を除くと自らを第三者と捉えている人が多いのではないか。それは、原発容認派がいまだに過半数という、直近の世論調査の結果から窺えるように思う。
だが我々は本当に第三者なのか。例えばハンナ・アーレントが書いた『イェルサレムのアイヒマン』を読むと、その確信がぐらぐらと揺さぶられることになる。アイヒマンはナチス親衛隊の隊員で、第2次世界大戦中に数百万のユダヤ人を強制・絶滅収容所に送り込んで死に至らしめた、いわゆる「ユダヤ人問題の最終解決」の実務を担った官僚だ。終戦後、アルゼンチンに逃亡したが、イスラエルの諜報機関モサッドに捉えられ、イェルサレムで裁かれて絞首刑に処された。裁判では一貫して「自分は命令に従っただけ」と主張したが、アーレントは「政治においては服従と支持は同じものなのだ」と一蹴している。
この本には「悪の陳腐さについての報告」という副題が添えられている。アーレントの筆は冷徹に、法廷でのアイヒマンの主張がいかに陳腐であったかを描き尽くす。さらに「アイヒマンという人物の厄介なところはまさに、実に多くの人々が彼に似ていたし、しかもその多くの者が倒錯してもいずサディストでもなく、恐ろしいほどノーマルだったし、今でもノーマルであるということなのだ」と書き加える(大久保和郎訳)。そこで我々は気づかされる。我々の誰もがアイヒマンと同様の蛮行を犯すかもしれないということに。アイヒマンは我々に潜在する多種多様の可能性の一様態であり、その意味で我々はホロコーストの第三者たりえず、それどころか加害者の一部を成しているということに。
同様に我々は被害者の一部を成しているとも言えるだろうが、加害者の場合とはかなり異なる。差別や戦争や虐殺の犠牲者になる可能性は誰にでもあるけれど、それはまったく受動的な、いわば事故にも似た偶発的災難であって、「悪」のように能動的で遍在的なものではないからだ(上述のアイヒマンとアーレントの主張を比べてみてほしい。前者が「自分は受動的だった」と述べているのに対し、後者は「いや、あなたは実は能動的だった」と喝破している)。
ホロコーストや広島・長崎やルワンダの犠牲者たちは、自らに咎がないのに、相手から勝手に選ばれてしまった。誰もが「被害者への共感」と口にしたがるけれど、人が共感するのは、自分と同じように考える(かもしれない)、あるいは行動する(かもしれない)者に対してのみである。彼らが「選ばれ」たのは選挙や試験などにおいてではなく、完全に受身であって、自らの考えによるものでも行動でもない。だから、論理的に被害者への共感は不可能だということになる。
この写真集を見れば、そんなことは言わずもがなだろう。ジョゼットにもトマスにも、ステラにもクロードにも、ジャスティーンにもアリスにも、我々は共感などできない。ただ息を呑んで、目を背けることなく写真を見つめ、母親たちが語る凄惨な物語を読むことで精一杯だ。彼らに対して「がんばって下さい」などと言うのは、控えめに言っても配慮が足りず、不誠実で無責任でさえある。我々はジョゼットを暴行し、ステラを孕ませ、ジャスティーンの家族全員を殺したフツの民兵たちにしか共感できない。それが、吐き気を催させるほど不快であり、思考を停止させられるほど信じがたい行為であったにせよ。
母親たちの中で静かな笑みを浮かべているのは、p.78-79のイベットだけだ。彼女の言葉を読むと、この微笑みはある種の悟りに基づくもののように思えて二重に心が痛む。想像を絶した経験がイベットを「悟り」へと導いたというわけだが、彼女の経験にも「悟り」にも、やはり我々が共感することは不可能だろう。
我々は自身の内部にフツの民兵を抱えている。ナチスやポル・ポトや原発の推進者たちも抱えている。彼ら加害者にこそ思いを馳せ、共感し、深く理解しなければならない。もちろん、陳腐な「悪」を称揚するためにではない。二度と出現させないために、である。


この目は見たことがある、と思った。思い当たったのは、パレスチナ映画『D.I』を撮ったエリア・スレイマン監督の目だ。プロモーションで来日した2003年、ティーチインの司会を務めた際に会ったのだが、イスラエル占領地区で繰り広げられる超現実主義的ナンセンスコメディとも呼ぶべき自作と同様に、四六時中ジョークを放っていた。
だが、目だけは笑っていなかった。あまりにも非日常的な日常を送っていると、ジョークが研ぎ澄まされる一方、感情は鈍化し、はては凍結されるのではないか。そんなふうに思わざるを得ないほど、外界を拒絶しているように見えた。
その目に似ている。母親たちの目も、子供たちの目も。ほぼすべてがカメラ目線で、したがってレンズを通して、我々読者を正視しているように思える。この視線にきちんと向き合うのは容易ではない。誰もが目を背けたくなるのではないだろうか。
世の中の多くの物事において、人は当事者と第三者に分かれる。それが人の手になる災厄だった場合、当事者は加害者と被害者に分けられる。つまり人災が起こった場合、人は「加害者」「被害者」「第三者」に分かたれることとなる。
『ルワンダ ジェノサイドから生まれて』の読者たる我々は、言うまでもなく第三者であるだろう。ルワンダは遠く離れている。紛争は我々が引き起こしたものではないし、関わってもいない。我々は人を襲ったことも犯したことも殺したこともなければ、襲われたことも犯されたことも殺されたこともない。だから我々は加害者でも被害者でもありえない。
同じことは同時代に自国外で起こったあらゆる人災について言えるだろう。ホロコースト、アパルトヘイト、アジア・アフリカ・東欧・中南米諸国における強権政治と虐殺、ヴェトナムやアフガニスタンや湾岸諸国への空爆、文化大革命、チェルノブイリ、天安門、9.11......。日本人にとっては、国内で起こり、被曝者がいまも苦しむ「広島・長崎」と、同じく現在進行形の「フクシマ」は事情が異なる。だが、本稿を書いている4月末時点では、被災地の方々を除くと自らを第三者と捉えている人が多いのではないか。それは、原発容認派がいまだに過半数という、直近の世論調査の結果から窺えるように思う。
だが我々は本当に第三者なのか。例えばハンナ・アーレントが書いた『イェルサレムのアイヒマン』を読むと、その確信がぐらぐらと揺さぶられることになる。アイヒマンはナチス親衛隊の隊員で、第2次世界大戦中に数百万のユダヤ人を強制・絶滅収容所に送り込んで死に至らしめた、いわゆる「ユダヤ人問題の最終解決」の実務を担った官僚だ。終戦後、アルゼンチンに逃亡したが、イスラエルの諜報機関モサッドに捉えられ、イェルサレムで裁かれて絞首刑に処された。裁判では一貫して「自分は命令に従っただけ」と主張したが、アーレントは「政治においては服従と支持は同じものなのだ」と一蹴している。
この本には「悪の陳腐さについての報告」という副題が添えられている。アーレントの筆は冷徹に、法廷でのアイヒマンの主張がいかに陳腐であったかを描き尽くす。さらに「アイヒマンという人物の厄介なところはまさに、実に多くの人々が彼に似ていたし、しかもその多くの者が倒錯してもいずサディストでもなく、恐ろしいほどノーマルだったし、今でもノーマルであるということなのだ」と書き加える(大久保和郎訳)。そこで我々は気づかされる。我々の誰もがアイヒマンと同様の蛮行を犯すかもしれないということに。アイヒマンは我々に潜在する多種多様の可能性の一様態であり、その意味で我々はホロコーストの第三者たりえず、それどころか加害者の一部を成しているということに。
同様に我々は被害者の一部を成しているとも言えるだろうが、加害者の場合とはかなり異なる。差別や戦争や虐殺の犠牲者になる可能性は誰にでもあるけれど、それはまったく受動的な、いわば事故にも似た偶発的災難であって、「悪」のように能動的で遍在的なものではないからだ(上述のアイヒマンとアーレントの主張を比べてみてほしい。前者が「自分は受動的だった」と述べているのに対し、後者は「いや、あなたは実は能動的だった」と喝破している)。
ホロコーストや広島・長崎やルワンダの犠牲者たちは、自らに咎がないのに、相手から勝手に選ばれてしまった。誰もが「被害者への共感」と口にしたがるけれど、人が共感するのは、自分と同じように考える(かもしれない)、あるいは行動する(かもしれない)者に対してのみである。彼らが「選ばれ」たのは選挙や試験などにおいてではなく、完全に受身であって、自らの考えによるものでも行動でもない。だから、論理的に被害者への共感は不可能だということになる。
この写真集を見れば、そんなことは言わずもがなだろう。ジョゼットにもトマスにも、ステラにもクロードにも、ジャスティーンにもアリスにも、我々は共感などできない。ただ息を呑んで、目を背けることなく写真を見つめ、母親たちが語る凄惨な物語を読むことで精一杯だ。彼らに対して「がんばって下さい」などと言うのは、控えめに言っても配慮が足りず、不誠実で無責任でさえある。我々はジョゼットを暴行し、ステラを孕ませ、ジャスティーンの家族全員を殺したフツの民兵たちにしか共感できない。それが、吐き気を催させるほど不快であり、思考を停止させられるほど信じがたい行為であったにせよ。
母親たちの中で静かな笑みを浮かべているのは、p.78-79のイベットだけだ。彼女の言葉を読むと、この微笑みはある種の悟りに基づくもののように思えて二重に心が痛む。想像を絶した経験がイベットを「悟り」へと導いたというわけだが、彼女の経験にも「悟り」にも、やはり我々が共感することは不可能だろう。
我々は自身の内部にフツの民兵を抱えている。ナチスやポル・ポトや原発の推進者たちも抱えている。彼ら加害者にこそ思いを馳せ、共感し、深く理解しなければならない。もちろん、陳腐な「悪」を称揚するためにではない。二度と出現させないために、である。


