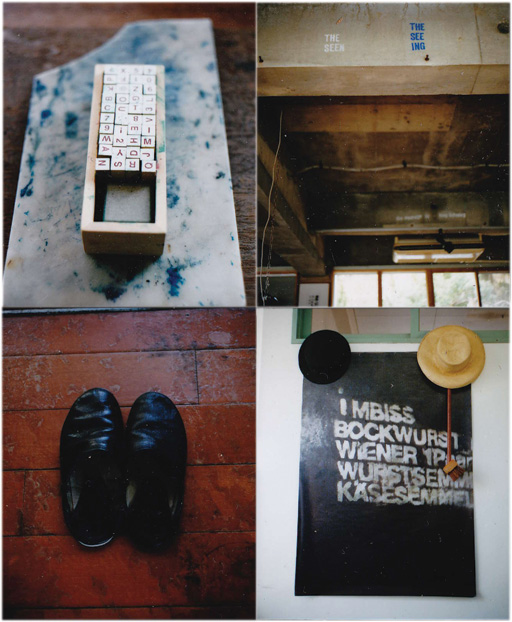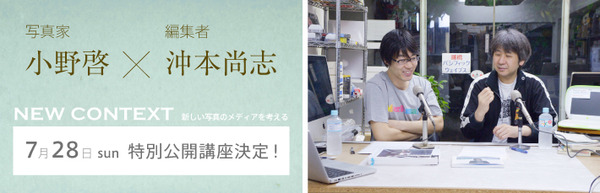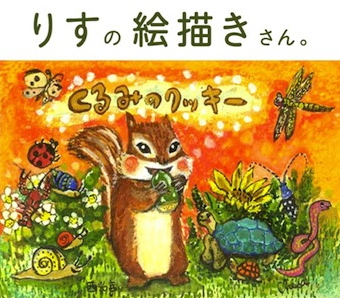カスピ海が世界でいちばん大きな湖なのは知っていても、そこにいくつの国が面していて、それがどこの国なのかを言い当てられる人は少ないのではないか。
解答と言うと、東から時計回りに、トルクメニスタン、イラン、アゼルバイジャン、ロシア、カザフスタンの5国である。そうか、と思うものの、無惨なほどそれ以上の感慨が浮かんでこない。多少の知識があるのはロシアとイランで、ほかの3国についてはどんな場所なのかイメージできない。
『対岸』はカスピ海に面したこの5国の沿岸で撮影されたもので、今年度の木村伊兵衛賞を受賞した。見たこともないような奇妙な様式のビル、派手できらびやかだが、どこと特定しづらい装飾的な室内インテリア、岩山に建つ古いアパートから突きでた無数のパラボナ・アンテナ、湖に携帯電話をむけて撮影している黒装束の女性たち、天然ガスの採掘場なのか岩のあいだの夜空を昼間のように明るく照らすライト群......。
過去にこのエリアがこのように撮影されてきたことはあるだろうか。海外には、カスピ海に生きる人々の暮らしや産業を追ったコーヒーテーブルブック的な写真集があるかもしれない。だがこれはカスピ海を撮った写真集ではない。写真家の関心は水域ではなく、そこに面した国々にある。
「対岸」というタイトルにもそれは現れている。「沿岸」ではなく「対岸」。湖の周りをめぐるのではなく、反対側に視線を投げかけるという意図が感じられる。西の黒海も複数の国に囲まれているが、あちらはボスポラス海峡のところが開いている。だがカスピ海は流出する川のない完全に閉じた円の空間なのだ。
トルクメニスタンの対岸にはアゼルバイシャが、カザフスタンの対岸はイランが、ロシアの対岸にはトルクメニスタンとカザフスタンがある。東と西、北と南が、この巨大な空隙を挟んで出会っているような不思議さを感じずにいられない。現代では対岸に行くことはなく、おそらく両岸を結ぶ空の便すらも少ないと思うが、かつては水運によって頻繁に行き来がされていただろう。
さて、ここから本題の写真に入りたいのだが、すでに書いたように私はそれぞれの国の文化についても、現在の国境線が引かれた事情についても知識を持っていない。知識がないということは、写っているものの意味を読み込めないということ、表面的にしか見られないということだ。ということをまず告白しておくとして、単純に写真のおもしろさに惹かれてページを捲っていった。知らない土地に降り立ち、街を歩く。手がかりのないまま、幼い子供と同じように目をキョロキョロさせながら歩く。将来ともその地に行くことはないと思うから、これが最初で最後のような気持ちで一点一点に見入る。
国別にレイアウトされているので、どの写真がどこで撮られたかは一目瞭然である。だが写真を見ているときの私は、国ごとの差異を見いだそうとする意志と、差異がないことに肩入れしようとする意志とに引き裂かれている。そのどちらの気持ちにも嘘はない。
差異を見いだすのは知的な視線である。よく目をこらせば写真によっては、文字、人の顔、国家元首の肖像写真、宗教建築など、国を特定できる手がかりが見つかる。それを探しだして理解を深めようとする。
もう一方の視線は、それとはまったく逆で、どの国のあまり差がないなあ思いつつ見ている。こちらのほうが現在の自分に正直だろう。たとえばパリのエッフェル塔のようなよく知られたシンボリックなものがない。人種的な差もわからず、文化的な記号が見いだしにくい。その代りに共通して浮かび上がってくるのは、街路が雑然としていること、建築様式が独特なこと、経済的に豊かそうには見えないこと(道路がガタガタで、ゴミが散乱している)、土地も肥沃そうではないこと(岩山や荒れ地が多い)......。
多少なりとも情感が感じられるのはロシアの章で、文化の厚みのようなものが伝わってくるが、ほかの4国はノイズが多く、文化的な記号が錯綜していて、それが少しもほどけないことに圧倒される。自分のまったく知らない場所が、彼らにはとても親しい場所であるということに驚き打たれることは東京を歩いていてもあるが、それが想像を超えるレベルにあり、圧倒的な「他者」との遭遇にめまいを覚える。
カスピ海と日本列島はほぼ面積が同じで、水域と陸地を逆転させると、閉じている島国=日本と、閉じている水域=カスピ海はポジネガの関係になる。それに気がついたとき、このプロジェクトの根っこにぶち当たったような気がした。もし「対岸」をキーワードに沿岸の5国を撮影したこれが世界初の試みだとしたら、日本の写真家だから発想できたということがあるかもしれない。世界最大の湖を挟んで5つの国がむきあっているという事実には、島国にいる私たちの想像をかき立ててやまない何かある。ツボを押さえられたような刺激が走る。